昔は鮨を家で作るのは結構ハードルが高かったですが、今は、酢飯を簡単に作れる炊飯器も出てきましたし、SCMの進化により上質な刺身も簡単に手に入ります。炙りを簡単に作れる家庭用バーナーも安価で購入できますし、軍艦用の高級海苔も通販で買えます。ということで、かなり本格的な鮨が家庭で楽しめる時代が来ました。
酢飯
炊飯器で酢飯を作る時代
昔は酢飯というと“すし桶+うちわ+職人の手”が定番でしたが、
最近の炊飯器は**「すしモード」を搭載しており、
家庭でも温度と水分を自動調整してくれる**ようになっています。
つまり、素人でも「酢の効いたしっとりシャリ」を再現できる時代です。
米の選び方
酢飯は、普通の白ご飯よりも「粘りが少なく、粒が立つ米」が理想。
ササニシキが本格派の風味が出て、あっさり系で職人が愛用している米です(福岡の「夢つくし」や「元気つくし」でもよい)。
炊飯時の水加減
すしモードを使うと自動で調整されますが、手動でやる場合は 通常より5〜10%ほど水を減らす のがコツ。酢を加えるため、水っぽくならないようにするためです。
基本のすし酢(2合分の目安)
調味料 分量 備考
米酢 大さじ3 まろやかなタイプが理想(穀物酢より酸がやさしい)
砂糖 大さじ1 酸味を和らげるため
塩 小さじ1弱 ミネラル塩を使うと味が深くなる
👉 これを炊き上がり直後に混ぜる。
作り方手順(炊飯器のすしモード使用)
- 米を研ぐ(2〜3回程度でOK。研ぎすぎ注意)
- 30分浸水(粒を均一に吸水させる)
- すしモードで炊く 水はやや少なめ(酢をいれるため調整)
- 炊き上がったらすぐに釜を開け、うちわで軽く蒸気を逃がす
- すし酢を回しかけ、しゃもじで切るように混ぜる(つぶさない)
- 広げて冷ます(扇風機や団扇で軽く風を当て、ツヤを出す)
→ 10分以内に冷ますのが理想。
ポイント:温度と水分の黄金バランス
- 熱いうちに酢を入れる:酸がまろやかになる
- 混ぜすぎない:粘りを防ぐ
- 人肌(約35℃)まで冷ます:握りに最適な温度
補足:一晩冷蔵はNG
酢飯は時間が経つと酢が飛び、米が硬くなる。
作ったら当日中に使うのが基本。
残すならラップで包んで冷凍→レンジで人肌に戻すのが次善策。
ネタ
市販の刺身パックを買ってきてそれを鮨ネタにしましょう。
鮨は「酢飯+ネタ」ではなく「温度と香りの調和」
おいしい鮨は、単に刺身を乗せたものではありません。
酢飯の“香りと温度(人肌)”に対し、
ネタ(刺身)はわずかに冷たい温度差を残すことでバランスが生まれます。
素人でも、この温度差を意識するだけで一気に“鮨らしい味”になります。
作業中、ネタは保冷剤を敷いたトレイの上に、シャリは人肌を保てるよう蓋付きの器に入れておく。温度管理を徹底するのも大切です。
変わり塩:ネタに振る塩として、抹茶塩、柚子塩、トリュフ塩などを用意すると、醤油なしでも楽しめます。
ネタに向く刺身の条件
| 種類 | 特徴 | ポイント |
|---|
| マグロ | 鮮度が命。赤身〜中トロまで対応 | 表面を軽く拭いて乾きを防ぐ |
| タイ・ヒラメ | 身が締まり、酢飯と相性抜群 | 塩を軽く振って10分置くと香りが立つ |
| サーモン | 油のりがよく食べやすい | 酢で軽く締めると鮨に合う |
| 貝類(ホタテ・アワビなど) | 噛むほど旨味が出る | 軽く炙って香りを引き出す |
| 白身魚(スズキ・カレイなど) | 上品で透明感がある | 昆布締めで旨味を凝縮 |
ネタの整え方(家庭版)
買ってきた刺身をペーパーで軽く押さえる
→ 余分な水分を取ることで味がぼやけない。
冷蔵庫で15分ほど冷やす
→ 酢飯より少し冷たい温度にする。
切り方を“やや厚め”にする
→ 素人が薄く切ると食感が不安定。2〜3mm厚で十分。
握る直前に包丁の刃を湿らせて切る
→ 美しい断面と口当たりを保てる。
ネタの簡易保存(半日~1日)
| 方法 | 内容 | 効果 |
|---|
| 塩締め | 塩を軽く振り10分置き、水分を拭く | 身が締まり臭みが消える |
| 酢締め | 米酢に1〜2分漬けて表面を引き締める | 保存性と風味UP |
| 昆布締め | 昆布で挟みラップして半日冷蔵 | 旨味が移り、ねっとり食感に |
※特に白身魚は、昆布締めが最もおすすめ。
火を使うアレンジ(炙り系)
- マグロ炙り:表面だけ軽くバーナーで炙り、香りと油を出す
- サーモン炙り:半分だけ炙ると甘味が強調される
- 貝類炙り:ホタテやアワビは焦げ目が“旨味の香り”になる
→ 炙りを入れると、家庭でも“高級店の香り”に近づきます。家庭用バーナーは安いです。ガスボンベはコンビニでも売っています。
方法
| 方法 | 内容 | ポイント |
|---|
| バーナー炙り | ネタの表面を10cmほど離して2〜3秒ずつ | 炙りすぎない。焦げ香は「香りづけ」 |
| フライパン炙り | 熱したフライパンにサッと表面を当てる | 油は引かず、1〜2秒で引き上げる |
| トースター炙り | 網の上で1分、予熱強め | 均一な焼き色で簡単 |
肉握り
「A5和牛の肉握り」「ローストビーフ握り」「炙りサーロイン握り」など。
鮨の組み立て方:握り・軍艦・手巻きの違いとコツ
1.握り鮨:シンプルほど奥が深い
基本の比率
- ネタ:酢飯 ≒ 1:1
- 酢飯:25〜30g(ピンポン玉1個弱)
● 手順(素人版)
- 酢飯を軽く握って空気を含ませる(強く握らない)
- ネタの裏にわさび少量を塗る
- 上にのせて、指で軽く整える
- ネタとシャリが“ふわっと一体”になる程度に圧をかける
👉 握りは「形を作る」より「空気を残す」意識。
プロのように固める必要はまったくありません。
● 素人でも成功するコツ
酢飯は人肌、ネタは少し冷たい温度差を保つ。
わさびは“香りづけ”であり、辛味ではない。
握る直前に手を軽く水+酢で湿らせる(“手酢”)。
→ シャリが手につかず、香りが立つ。
2.軍艦巻:香りと食感を包む「海苔の芸術」
基本構造
- 酢飯を小さく丸める(20〜25g)
- 高さ3cmほどに海苔を巻く(幅1/3カットが標準)
- 上に具材(イクラ・ウニ・ネギトロ・マグロ納豆など)をのせる
● コツ
- 海苔は巻く直前に炙る(香りが立つ)
- 酢飯の表面をやや平らにして具を安定させる
- 具材は「盛る」というより「軽く置く」
海苔
素人が家庭で鮨を作るとき、プロとの差を決定的に感じるのが海苔の香りです。高級海苔を使うべし。特に有明海産は柔らかく甘い香り。
3.手巻き鮨:素人が一番自由に遊べる形式
構造
- 焼きたての海苔を1/4〜1/3カット
- 酢飯を細長く軽くのせ、具材を中央に配置
- 巻いてすぐ食べる(海苔が湿る前に)
コツ
- 酢飯少なめ、具材たっぷりが美しい比率
- 手巻きは「香りを包む料理」
→ 海苔の香りを最大に生かすには、熱い酢飯NG(40℃以下) - 手巻き向け具材:タイ、アジ、ホタテ、卵焼き、キュウリ、ツナ、納豆など

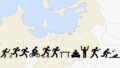
コメント